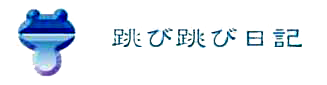

皆様お久し振りです。
無事引っ越しました(^^)
ご迷惑をおかけした皆様、いろいろとありがとうございました。
まだ我が家はえらいことですが、
少し落ち着いてきました。
これからは心機一転、頑張るぞ〜!
→ベランダに寝転んでパチリ。
本日は久しぶりによい天気となりました。


何やらタイムスリップ日記になってきたぞ。(^^)
高知県立美術館の「コムパル」ツアーに参加してきました。
行き先は、「大阪市立美術館で開催中の《佐伯祐三展》です。
前日大雨、朝、集合場所の高知駅に向かう途中もしとしと雨で、お天気が心配でしたが、なんとか道中は無事に晴れ、道路状況にも恵まれて、心地よい旅でした。
この《大阪市立美術館》、何年か前に《フェルメール展》を見に来たことがあります。以前来たときはもっと暗い印象でしたが、館内なんだかすっきり(?)したような。展示物の違いのせいだけではないような気がします。
このところの多忙のせいで、展覧会にはほとんど無知のまま行きましたが、道中の解説(このツアーは学芸員さんが添乗してくださるため、いろいろ考えることができておもしろいのです。)と実際に作品を見ることができて、はるばる来たかいがあったと思いました。
このごろ思うのですが、芸術に興味があるということは、人間に興味があるということなのかなぁ。…と。ほかに、これほど人の人生がにじみ出る分野って、ちょっと思いつかないわけで。
改めて考えたのでした。
ちょうど当日は篠館長の講演会もあり、(篠館長は高知県立美術館の前館長だった方です)ひさしぶりに客席からお姿拝見してきました。
…人間の人生について話をされていました。何かにまともに向き合うということは、ほんとに、大変です。
…聞きに来られてよかったと思いました。
何をするにも、良い季節の到来です。
『第62回高知県展』(会場/高知県立美術館・高知市文化プラザかるぽーと)見に行ってきました。
会場には、どこもかしこも、見渡す限りぎっしり・ずっしり、作品が並んでいました。
このところ、いろいろな展覧会を立て続けに観る機会を持って、考えることがいろいろあります。
目には見えない『たましい』やら『心』の存在がはっきりと作用して、芸術作品はどのようにでも姿を変えていく。
『観るべきものがある作品』を、作るには、それなりのものを込める力を持たなければ…。
このところ、そのようなことを考える旅となってきました。
あらゆる作品、観ることで鍛えられていくようです。
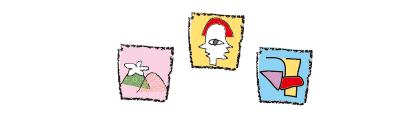
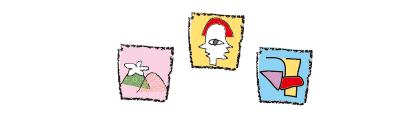
高知県立美術館に、彫刻家・若林奮さんの『石枕(せきちん)』という作品があります。10月10日の5回目の命日にあわせて、いつもは触れることのできない作品の特別公開と、座談会がありました。
『土佐桜』という、美しい薄いピンク色が特徴の大理石を、丹念に人の手で「はつる」という作業をへて、美術館のせせらぎの中にたたずむ彫刻として設置されたのが、今から10年前のことだそうです。製作当時にアシスタントをされていて、現在は美術作家として活躍されているお二人のかたや、製作を取材に来た新聞記者、彫刻や展覧会の担当学芸員が、それぞれの立場からいろいろなエピソードを話してくださいました。
ものを作る人間として興味深いこともありました。
『よく質問する方だった』という言葉が印象的でした。…いろいろな素材を使って製作する上で『人の意見に耳を傾ける』というのは大切な姿勢だったのではないでしょうか。…なるほど、と思いました。
5年前、若林奮さんが亡くなったことを、私は新聞で読んで知りましたが、…なんとその訃報を、記事を書いた新聞記者に伝えたという方が、今日の座談会に来ていました。…つくづく、人のご縁とは不思議なものです。
昔からの知り合い(?)と、当時のことを知らない私のようなものが加わって、一つの場所に集っている。これも作品に魅力あればこそでしょうか。
若林さんの作品、硫黄の水玉(すみません、題名をど忘れしました。)の作品が好きです。


10/11に、『踊りにいくぜ!vol.9』(高知県立美術館ホール開催)を観てきました。
高知県開催は今年で3回目、私も今のところ毎年通い続けており、年ごとに違う顔ぶれのダンサーが、いろいろな趣向を凝らしてコンテンポラリーダンスの舞台を届けてくれます。
昨年、今年と日本のダンサーのみならず、海外からのダンサーも参加しており、さらに地元高知県選出のダンサーも加わり、それぞれに個性があって、見応え十分の公演でした。(出演:七転八倒/高知、山賀ざくろ×泉太郎/東京、富野幸緒/東京、ピチェ・クランチェン/タイ、KIKIKIKIKIKI/京都)
今回とても印象的だったのは、昨年に続いて、アジア圏から出演(タイ)のダンサーの方が見せてくれた踊りでした。16歳の頃から、タイの古典仮面舞踏『コーン』を学び、そのうえで、現代の表現を模索しているとのこと。
観ているうちに、ふと、『お寺などに安置されているはずの仏像が動くとしたら、こんな感じなのでは』…と思いました。しかし、大きな意味での宗教性は感じられても、そこにはただ一つの宗教に縛られた息苦しさはなく、相対しているのは一つの『宇宙』、ひとりの『人間』が何か大きな秩序を持った世界に、対峙しているように思えました。
文化の上ではやはり、同じアジアという背景で、動きのそこここのなかには、いつかどこかで見慣れた共通の感覚があり、いくら生活が西洋化されても、私の中にも脈々と受け継がれているその感覚が、私の中にも存在していて、私という人間の一部として影響を及ぼしている。
昨年に観る機会のあった西洋のダンサーの踊りとは、明らかに違う。そういうことを考えられるのも、いろいろな主義主張手法の表現が入り交じることを可能とする、このダンスプロジェクトならでは、という気がします。
しかし、鍛えられた肉体と、意味を持つ体の動き。
毎回すごいなと、思わずにはいられません。
ぜひ来年も開催してほしいものです。楽しみにしています。(^^)
満月です。
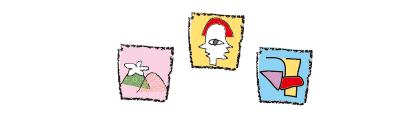
昨夜から、本格的に『秋物』にかかっています。…毎回、季節に追いつくのが大変で、もう少し早くと考えているのですが、やはりこのぐらいのスピードになってしまう。身体が季節を取り込めないうちは『何を作ってもだめ』という感じがあって、まぁ毎回、『生物だなぁ』…と考え深くもありますが。この融通のきかないのはなんとかならんのか。
・・・毎回、やれやれなのでした。
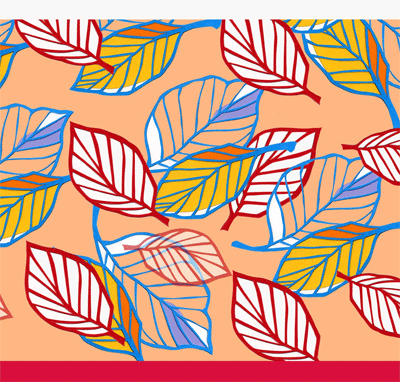
新しい柄にとりくんでおります。季節が秋なので、秋の柄を、と思いつつ製作中です。
毎回悩むところですが、
まるっきり『新しいもの』というのは難しい。
苦労しないですぱっと思いつくこともありますが、稀です。
どこかに違う刺激を与えても、そやつがきちんと育つまでは作品としてはおぼつかない感じがします。
きっかけは何でもいいような気がするのですが、それが『育つ』ことが重要です。
…ローマは一日にしてならず。
本日もまた…。ううむ。
やっと、秋の新作ハガキが印刷されてきました(^^) 『柿』と『秋桜』・『柿と文鳥』です。
『柿』『秋桜』はコトリ堂さま、『柿と文鳥』は文鳥堂さまに置いていただくつもりです。
どうぞよろしくお願いします。
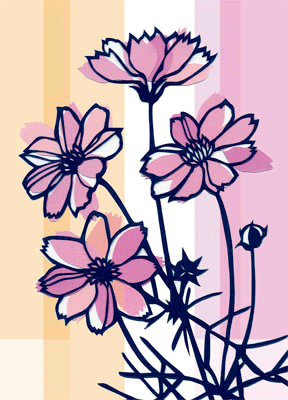

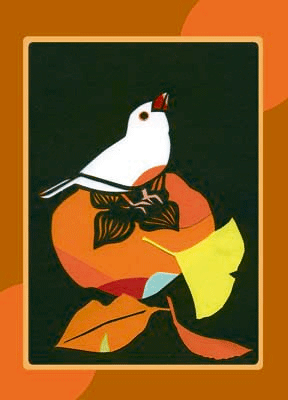
一昨日より始まった、『聖地巡礼 野町和嘉写真展』(12/14まで・高知県立美術館)に行ってきました。
野町和嘉さんは高知県出身の国際的な写真家で、高知ではこれまでにいくつも展覧会が開かれています。
本日は展覧会の関連イベント
『野町和嘉氏×佐伯剛氏(「風の旅人」編集長)対談』に参加してきました(^^)
まず、野町さんご自身の解説で作品のスライドを見せていただき、対談が始まりました。印象深かったことはいろいろありますが、
イスラム教の中心としての『メッカ』を撮った写真で、『この光景を見たとき、この黒い家を中心に同心円上に永遠に世界に広がっていくのが“イスラム教”なのだ、と理解した。』『砂漠の一つの集落は一つの井戸から成り立っていて、そのオアシスの外側には部族の墓があり、それは現在、そこで生きている集落の人間の数を上回っている。…水は神からの賜り物であり、一神教の神の慈悲や慈愛は日本のそれとは全く違う。』『日本で見かけるイスラムの写真は事件であることが大半だが、それでは伝わらない。』
そして、佐伯さんとの対談の中で、『野町さんはこれまでに、イスラム、キリスト、チベットなどの宗教を題材にした写真を撮っているが、5−6年前はインドは太刀打ちできないとおっしゃってインドの写真を撮らなかった。今回、野町さんがインドの写真撮影に臨んだことには、何か以前との心境の変化があるのか。』という問いかけに対して、『今回インドは、チベットから下って来たという感じがある。イスラムの世界を撮ったときには常に緊張していたが、インドは自然体で、リラックスして撮ることができた』と返答されていました。
そして被写体との距離についての話のなかで、『時間をかけて、知らないあいだに『気にならないような人間』になっていく。人々の間に入り込んでいくには、信念と図々しさが必要だ。』
あと、これは佐伯さんの言葉ですが『近頃若い人が写真を売り込みにくるが、それは『外側』をなでただけのものでって、「人間の顔」の内面にまでは迫れていないものが多い。』…などという意見が述べられていました。。
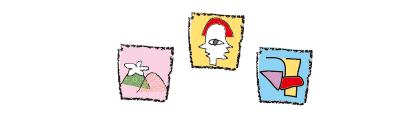
展覧会の写真には、『人間』について、『生と死』について、『宗教』について、一人の写真家の目を通して、見聞きし考えられたことの集積を、生きたものとして見る者に伝えくるリアルさがあります。
百聞は一見にしかず。
『生きる力が必要なときに見るものが芸術』だという佐伯さんの言葉も、日々、写真を『見る』ことによって向き合う人間の言葉として、とても確かなものに聞こえました。
展覧会は12月14日まで。一見の価値あります!


荷物の山から大捜索の末、出て来たビーズたち。
『かえるのたまご』にてお世話になっている、magnet council さんが、先日より再Openされました(^^)
かわいいぼっちゃんとともに新たな出発、今後ともよろしくお願いしますね。
…ということで、こちらも新作でお出迎え、と精を出しているのがこの状況であります。(しかしすでに間に合ってない!)
今年は旅やら夏バテやら引っ越しやらで、なかなか細かい作業が出来ませんでした。(やはり気持ちが落ち着かないと細かい作業は無理)とほほ…。
11月には納品して新作にしますが、こりゃがんばらにゃ〜!
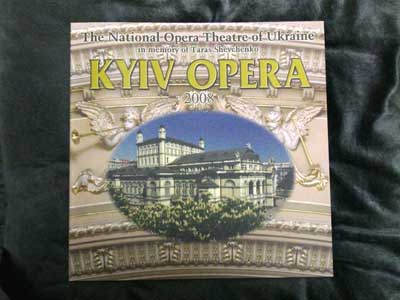
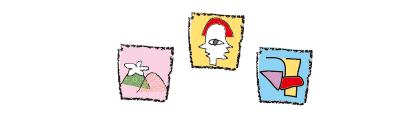
キエフ・オペラ『トゥランドット』
(ウクライナ国立歌劇場オペラ)/高知県立県民文化ホール 主催:高知新聞社、RKC高知放送
を見せてもらってきました。普段はあまりご縁のない世界なのですが、たくさんチケットをお持ちの方からお誘いいただきました。…何気なく行ったのですが、これが、すごい!!
総勢210名の引っ越し公演というだけあって、オーケストラの演奏、歌手の歌唱、衣装も舞台もすばらしく絢爛豪華で、見応えがあり驚きました。
『トゥーランドット』のお話は有名ですが、恐ろしいお姫様の役がほんとに真に迫る悪人ぶりだったため、カーテンコールのときには、途中で死んだ奴隷のリューに拍手が集まっていました。
何はともあれ、本日の舞台公演、見に行ってよかったです。お誘いくださった皆様、演者のかたがた、どうもありがとうございました。
日本全国で巡回しているようです。『トゥーランドット』は中国のお話なんですね。パンフレット見るまでは、中東のどこかの国かと思っていました・・・(^^:)。